日本刀鑑賞の手引 |
日本刀を鑑賞する時のポイントを説明します。ここではポイントだけの説明ですので、興味を持たれた方は専門書でご研究ください。
|
| HOME|居合道の世界|刀剣の世界|刀剣Gallery|リンク|更新履歴 |
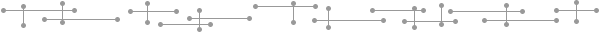 |
| 鑑賞ポイント |
日本刀は、世界無比の鉄の芸術品であり、我々の祖先は刀や甲冑のような武器や武具にも「美」を求め大切に扱ってきました。日本刀からはこの洗練された姿、鍛えられた地鉄、美しい刃文などを作り出された時代や流派と共に鑑賞していきます。 (1) 刀の姿 日本刀には、太刀、刀、脇差、短刀などがあります。 <太刀> 平安時代(12世紀)末期から室町時代初期まで腰に吊るして用いた刀で「反り」が高く65〜70cm位の長さがあります。 <刀> 太刀にかわり室町時代中期(15世紀後半)から江戸時代末期(19世紀中頃)まで使用され、60cm以上の長さがあり太刀よりやや短いです。太刀とは逆に、刃を上にして腰に指します。 <脇差> 約30cm以上60cm位迄のもので刀と同じく腰に指します。 <短刀> 約30cm以内のもので腰刀ともよばれているものです。 刀を垂直に立て握り拳が肩位の高さにして刀全体の姿を鑑賞します。刀の「反り」や刀全体から発する気品や優雅さを感じとります。 刀を全体の鑑賞するときには鍔元から切っ先に向かって見上げていくようにして鑑賞します。裏側を鑑賞するときも同様です。これは神聖な刀ですので、上から下に見ていくことは「見下げる」ことに通じるからでしょう。 (2)地肌 地肌には「杢目」「柾目」「板目」「綾杉」「松皮」などの種類がありますが、これは刀匠が鉄を鍛える時の重ね方の方法によってできるものです。時代や流派により特徴があるので鑑賞するときのポイントとなります。 地肌を見るときは刀を斜めにして、自分の背後から光線をあてるとよく見えます。 (3)刃文 刃文には「直刃」「丁子」「互の目」「乱れ」などいろいろな種類があります。刀匠が刀を鍛えた後、焼入れという工程がありますがこのときに土を刀身につけて水に浸け急冷します。この土のつけ方により独特の模様や変化が現れてきます。 刃文を見るときは刀を斜めにして、電球の光に透かして見ると良く見えます。 (4)その他 以上のほか、中心(なかご)に彫られている銘(刀匠の名前)を確認したり、切っ先(刀身の先端)や刃文の中に現れている「働き」を鑑賞します。 刃のある刀身には、直接に手を触れないよう注意してください。危険であるともに錆の原因にもなります。もし地肌や刃文を見るときに片方の手で刀身を支える場合には、「袱紗」かやわらかい布を使用します。 前にも述べましたが、刀を鑑賞する前、終わって刀を戻すときには必ず忘れずに軽く拝礼しましょう。 |
 |
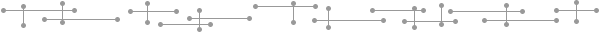 |
| HOME|居合道の世界|刀剣の世界|刀剣Gallery|リンク|更新履歴 |
|

