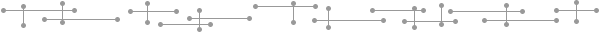居合道は、室町時代すなわち足利三代義満が京都室町に幕府を置いたころから始まり400年以上の歴史がある。戦国時代は乱世のならいで弱肉強食の世の中であり、何時如何なる場合に不意打ちを受けるかもわからないので、これに対処できる武術として発達してきた。現在では居合は、人(個人)を完成するために、日本刀を用いて心身を鍛錬しながら刀の操法を学ぶものである。
私は早くから日本刀そのものに興味があったことと、体力をつけ健康増進と精神修養を行い長くつきあっていけるものとして、この居合を続けている。
剣の技には、最初から刀を構えて戦うケースと抜刀すると同時に仕掛けるケースがあり、前者を「立合い」、後者を「居合い」という。武士同士が勝負を決する時には、「居合い」の心得のある者のほうが有利であった。では「居合い」とはどのようなものかというと、基本的には「抜き付け」一刀目と「留め」の二刀目だけである。精魂込めて繰り出した最初の一撃で相手を倒せなかった場合、慌てずに次の攻撃に移って留めをさす。どのような場合でも臨機応変のリアクションをごく自然に行える能力を身につけられるものである。この能力は当時の実践の場では極めて重要な技であったと思われるし、現在の変動の激しい社会においても通じるものがあると思う。 |
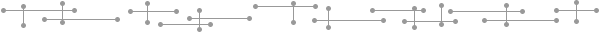
 居合道とは
居合道とは