居合道における知識と活用 |
居合道でのいろいろな知識とその活用に関して述べます。
|
| HOME|居合道の世界|刀剣の世界|刀剣Gallery|リンク|更新履歴 |
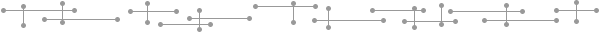 |
| 礼儀作法 |
武道は礼儀に始まって礼儀で終わります。最近の若い人達の中には礼儀をわきまえていない人が多いと言われていますが、これは礼儀作法そのものを知らないからだと思います。親もあまり言わないし、周りも注意しないからでしょう。武道の礼儀作法とまで言わなくても少なくともこれを心得ていれば、おのずと普段の所作の中に現れてくるものです。 武道における礼儀作法について簡単に説明します。 武道の稽古を始める前に ○上座に向かって「武神」に立礼 ○教えをいただく先生方に正座し両手をついて礼 ○刀に対して正座し両手をついて礼 以上3回の礼を行います。 また稽古を終った後に ○刀に対して正座両手をついて礼 ○先生方に正座両手をついて礼 ○武神に立礼 ○同輩達に対して正座両手をついて礼 を行います。 正座両手をついてのお辞儀の仕方 ・正座し両足の膝頭間は軽く握り拳1つ分位あける。 ・両手の指は揃えてハの字型に左右の太股の上にのせる。 ・左手を床につけ続いて右手を床につける。 ・このとき両手の親指と残りの四指とで正三角形をつくる。 ・この三角形に鼻先を押し付けるような形でお辞儀をするが背筋を曲げず腰を浮かさずに行います。 ・相手が目上の人であれば、相手が頭を上げるのを気配で感じてから自分も頭を上げていきます。 ・このとき右手を引いて右ひざに戻し続いて左手をもどします。 ・最初の正座の姿勢でまっすぐ前を見ます。 以上ですがこのお辞儀の仕方のポイントは以下です。 1.両手を同時に床につけるのではなくまず左手から続いて右手の順で行い、手を戻すときは右手を先に引いてから続いて左手を引きます。 これは、何か事があれば常に右側に置いている刀にすぐ手を移せれるようにして、右手が塞がる時の「すき」を作らなくするためです。 2.頭を下げてお辞儀をする時は首の後ろが見えない角度で首と背筋をのばして行います。相手に首の後ろが見えているということは、それだけ「すき」を作っていることになります。また、お辞儀の姿も悪くなります。お辞儀をするのに頭を下げるのは、首を相手に差し出してどうにでもしてくださいということからお互いの信頼感を表す挨拶の表現となったようです。 3.両手で作った三角形に鼻を押し付けるように頭をもっていってお辞儀をするのは、もしお辞儀をしている途中に突然、頭を上から押し付けられた場合、この両手で作った三角形で鼻を保護し自分の身を守ることができるからです。 4.何事にも言える事ですが、同時に幾つかの動作をしないことです。一つ一つの動作を順序よくスムーズに行うことが綺麗にかっこよく良くみえるものです。 たとえば、パーティの時など、テーブルに座っていて前にあるグラスを持って立ち上がる場合、立ち上がりながらグラスをもつより、立ち上がって一呼吸してからグラスに手をやった方がカッコ良くスマートに見えます。 このように古来より行われているお辞儀の作法ひとつひとつに奥深いものがあり、現在でもいろいろな場面で応用していくことにより、他の人とはちがったエレガントでスマートな動作を行うことができると思います。 |
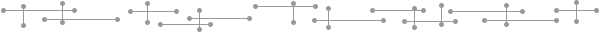 |
| <先の先> |
居合いは自分から攻撃を仕掛ける技ではありません。鞘に刀を納めたまま敵と相対し自分の身を守るために使用するのが前提です。居合に「鞘の内」という言葉がありますが刀を抜かずに相手に勝つことが最善であるという意味です。剣術は鞘の外にある刀で敵に相対しますが、居合いは鞘の中にある刀で敵に相対するという大きな違いがあります。敵が斬りかかってきて、自分の身に危険が及ぶ瞬間に抜刀した刀で敵の攻撃を受流し、擦り落としたあとに反撃にでる「後の先」(「ごのせん」)。まだ刀を抜いていないが、相手が明らかに攻撃を仕掛けようとしているのをいち早く察知し、先制攻撃を仕掛ける「先の先」(せんのせん」)がありますがいずれも自分の身を守るための危機管理の技であります。現在社会においては、この「先の先」はいろんなビジネスシーンで活用できると思います。パソコンにワクチンソフトを入れて常にウィルスに対応しているのもこの「先の先」なのです。今の社会では、この「先の先」の意識を常にもつことが大切なのです。残念ながら今の日本の国はまだ、この意識が低いようなのですが..... |
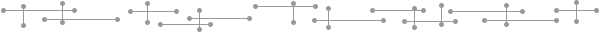 |
| <礼三息と残心> |
武道において「残心」という言葉があります。これは敵と相対して相手を倒した後も注意を怠らず、再び反撃してきた時にはすかさず倒せるように油断のない心を残すという意味です。特に居合いにおいては「納刀」時においても常に、この「残心」をもつことを要求されます。座礼の礼儀作法について前に述べましたが、立礼・座礼ともに相手とタイミングを合わせてお辞儀をすることが望ましく正しい姿勢を保ちながらお辞儀をすることが大切です。そのためにもお辞儀のやり方に「礼三息」と言う息遣いのやり方があります。 1.まず息を吸いながら身体をかたむけます。 2.次に動きが止まったところで息を吐きます。 3.さらに息を吸いながら元の姿勢に戻ります。 この2の動きが止まったところで息をはくことにより数秒の「間」がとれ、動作が美しくまたこころのゆとりが表われます。またお辞儀をして元の姿勢に戻った時、すぐに次の動作に移らず、数秒の「間」をとることが必要です。これが「残心」で、常に相手に対するこころを最後まで残すということになります。現在の慌しい日々の中で、何事につけてもこの「残心」を忘れないにすることが必要だと思います。 |
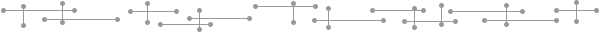 |
| <姿勢> |
居合いは、居業(正座)や立業において姿勢を正しくとることえを基本としています。正しい姿勢を保つポイントは、腰に意識をし背骨が腰に突き刺さるようなイメージで上体を上に伸ばします。また顎が前に出てしまうことも多いので意識して顎を引くようにします。 正座の場合はこぶし一つ分程膝を開けて座ります。ただ女性の場合は、居合い以外では膝を揃えて座ります。両手は親指と小指で中の三本指を少し締め付けるようにして少し膨らみを持たせて指を揃え、「ハ」の字にして太股の上に乗せます。脇は軽く卵を挟むような心持ちにします。 立ち姿は立ち業の姿勢と同じですが、両足については、足先を少し開きます。女性の場合は基本は平行に揃えますが、ヒールなど踵が高い履物の場合は安定が悪いので男性と同様に足先を少し開きます。歩くときは、姿勢を伸ばし、足を平行に出して歩くことがポイントです。後ろの足が外に向き易いので意識をすることが必要だと思います。 人の姿勢は、左右どちらかの肩が下がっていたり、猫背になり易かったりそれぞれ癖をもっています。まず、自分の癖を知って正しい姿勢を身につけるように、また常に修正しようという心がけをもっていくことが大切だと思います。 |
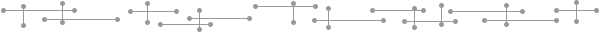 |
| <歩行(ナンバ歩き)> |
最近「ナンバ歩き」が見直されています。「ナンバ歩き」というのは江戸時代まで武士も庶民もごく普通に行っていた歩き方です。今は手足を交互に動かして歩きますが、「ナンバ歩き」は、左右の足と同じ側の左右の手を動かして歩く方法です。しかし、実際は左右の手はほとんど動かさずに、体をねじらないようにして歩く方法です。明治維新以後、外国の軍隊方式を導入してから日本人は、現在のような歩き方になったと言われています。最近、古武道研究家の甲野善紀さんがこの「なんば」を提唱されて実際短距離やバスケットボールなどのスポーツに取り入れられています。昨年、陸上世界選手権大会の男子200mで日本人初の銅メダルを獲得した末續選手はこのナンバからヒントを得た走り方をしたそうです。現在の歩き方の身体の中心を軸として歩くのは「ねじれ」が起こりロスがあるのに対し、ナンバですと左右の二軸による身体動作になるので、ロスが少なく効率よく歩けるということです。 |
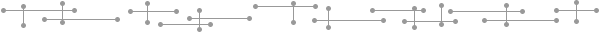 |
| HOME|居合道の世界|刀剣の世界|刀剣Gallery|リンク|更新履歴 |
|

