日本刀について |
一本の日本刀が出来上がるまでの過程を簡単に説明します。
|
| HOME|居合道の世界|刀剣の世界|刀剣Gallery|リンク|更新履歴 |
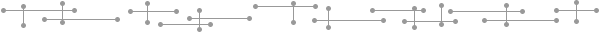 |
 日本刀ができるまで 日本刀ができるまで |
 |
一本の日本刀が、美しい拵(こしらえ)に収められるまでに、刀鍛冶が刀身を作った後、研師、白銀師、鞘師、彫金師、鞘塗師、柄巻師といった色々な職人さんの手を経る。さらに日本刀の材料となる和鉄を作る人や柄に巻く組紐を作る人まで数限りない匠の元に日本刀が完成するのである。 主な職人さんの内容 ●刀鍛冶(かたなかじ) 火と水と人間の力により、一塊の鋼から地金・刃文等の文様を持った刀身に作り上げる。砂鉄を原料とした玉鋼の「積み沸かし」から「銘切り」に至るまで約10余りの工程がある。 ●研師(とぎし) 刀鍛冶が作った刀身を研師が研磨することによりその切れ味と輝きが生まれる。刀鍛冶が鍛えた刀身いかに美しく仕上げるかは研師の腕にかかっている。研ぎとしては下地研ぎから仕上げ研ぎまで約10余りの工程がある。 ●白銀師(しろがねし) 日本刀には刀身が鞘に納まった時に鞘に触れるのを防いだり、柄と刀身を固定したりするための金具、つまり「はばき」というものがある。この「はばき」は、刀身一つ一つの形に応じて美的センスでもって製作される。 ●鞘師(さやし) 刀身を保護する白鞘や、鍔などの金具や塗りの施された拵の下地となる鞘を作る。刀身の保護と使い勝手を支える、究極の実用美がこの鞘にある。 ●塗師(ぬりし) 鞘を丈夫に美しく仕上げるために漆をぬる。ごく薄い層を支えるのは数多くの工程で何度も漆を塗り固めることによってその強度と美が生み出される。大きく分けて下地、中塗り、仕上げの工程がありすべて約20余りの工程がある。 ●柄巻師(つかまきし) 刀剣を手に持つときのグリップの部分を柄(つか)といいこの柄の部分を補強し手だまり良くする。柄下地から鮫革着せ、糸巻きの工程がある。 このよう幾つかの専門職人さんの手を経てやっと一本の美しい日本刀が出来上がるのだが、一人前になるには長年の熟練が必要なため、このような職人さんは年々少なくなってきている。 |
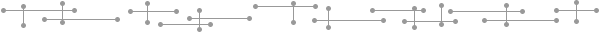 |
| HOME|居合道の世界|刀剣の世界|刀剣Gallery|リンク|更新履歴 |
|


